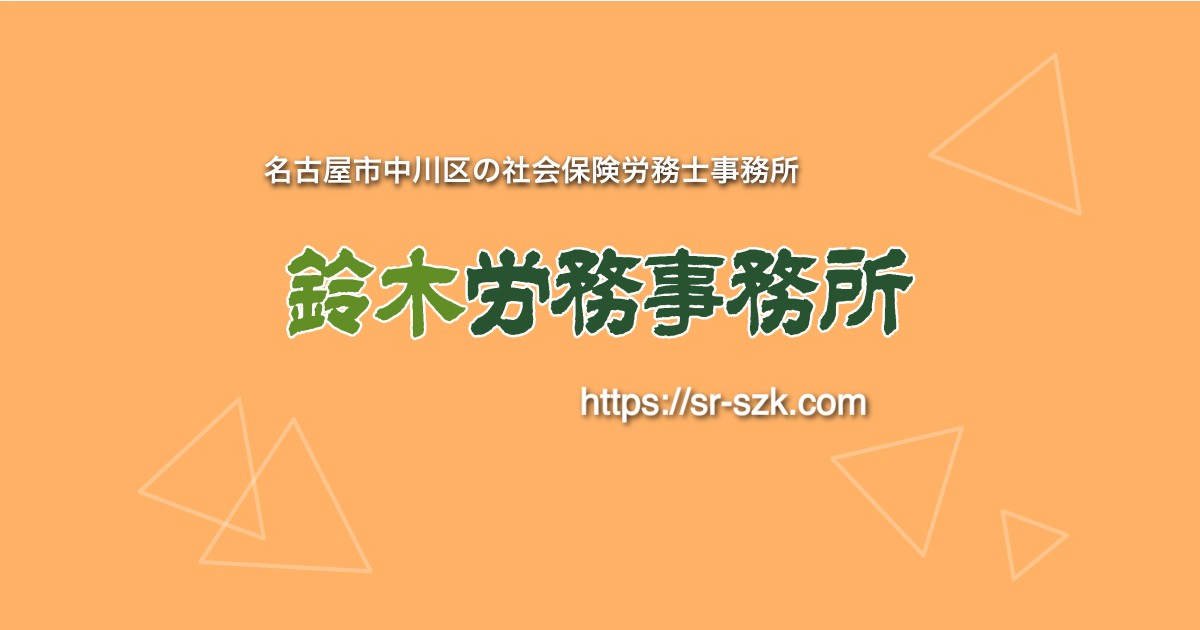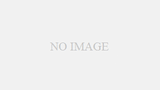2025年4月施行の育児・介護休業法改正に伴う就業規則の見直しポイント
2025年4月より、育児・介護休業法が改正されます(→こちら)。それに伴い、就業規則の改訂も必要になります。
今回は、厚生労働省が先日公開した「育児・介護休業等に関する規則の規定例(詳細版)」と、以前の規程例を比較し、法改正が就業規則のどの部分に影響を与えるのかを整理してみました。
法改正に伴い就業規則の改訂が必要となる主な内容
【2025年4月1日施行】
- 子の看護休暇の見直し
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加(選択肢として導入可能)
- 育児のためのテレワーク導入(努力義務)
- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(労使協定により除外できる範囲の縮小)
- 介護離職防止のための雇用環境整備
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
- 介護のためのテレワーク導入(努力義務)
【2025年10月1日施行】
- 柔軟な働き方を実現するための措置等
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
規程例との対応(条数は新規程例のもの)
第1条(目的)
- 「柔軟な働き方を実現するための措置等」の文言追加
第14条(子の看護等休暇)
- 名称を「子の看護等休暇」に変更(「等」を追加)
- 取得対象を小学校3学年修了までに拡大
- 取得理由の列挙(予防接種、健康診断、学級閉鎖、入園・入学式の追加)
- 労使協定により除外できる従業員の範囲を縮小(「入社6ヶ月未満の従業員」を削除)
第15条(介護休暇)
- 労使協定により除外できる従業員の範囲を縮小(「入社6ヶ月未満の従業員」を削除)
第16条(育児・介護のための所定外労働の制限)
- 小学校就学の始期に達するまでの子に対象を拡大
第19条(育児短時間勤務)
- 育児短時間勤務が困難な業務に従事する従業員を労使協定により対象外とする場合の代替措置として育児のためのテレワーク、育児のためのフレックスタイム制度の例を追加
第20条(柔軟な働き方を実現するための措置)
- 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できる措置を新設(努力義務)
- その他の柔軟な働き方の選択肢も規定
第21条(介護のためのフレックスタイム制度)
- 介護短時間勤務以外の措置例として介護のためのフレックスタイム制度を追加
第28条(円滑な取得及び職場復帰、制度利用支援)
- タイトルに「制度利用支援」を追加
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修実施を追加
- 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認項目の追加
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮について妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取を明記
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等について介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供を追加
就業規則の改訂に向けたポイント
今回公開された規程例は、2025年4月施行分だけでなく10月施行分も含まれています。
また、この規程例以外にも、柔軟な対応が可能な部分があります。
例えば、第28条の「介護休業及び介護両立支援制度等に係る研修の実施」に関しては、
- 相談窓口の設置
- 社内での事例紹介
といった別の方法も認められています。
自社の従業員のニーズや業務特性を踏まえた規定の見直しが重要です。
細かな文言の変更も含め、本稿を参考に自社の就業規則と比較し、2025年4月に向けた改訂準備を進めることをおすすめします。
【参考】
育児・介護休業法について:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
育児・介護休業等に関する規則の規定例:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
それでは今週のニュースPickupをどうぞ!!
日本年金機構
令和7年4月1日から現物給与価額(食事)が改正されます(3/14)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202503/0314.html
厚生労働省
令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)を公表します
~大学生の就職内定率は92.6%と、調査開始以降同時期で過去最高~(3/14)
厚生労働省と文部科学省は、令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、 令和7年2月1日現在の状況を取りまとめましたので、公表します。取りまとめの結果、大学生の就職内定率は92.6%(前年同期差+1.0ポイント)となりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00053.html
令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します
~学生アルバイトのトラブル防止のために~(3/14)
厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54645.html
第217回国会(令和7年常会)提出法律案
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案(3/12)
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
※ページの下の方にあります。
多様な働き方の実現応援サイト(厚生労働省)
「5分でわかる! 職務分析・職務評価入門」の動画をアップロードしました!(3/12)
正社員とパートタイム・有期雇用労働者の基本給について、職務内容や人材活用の仕組みなどに応じ、待遇差が妥当であるかを客観的に確認できる「職務分析・職務評価」について、解説しています。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/
明るい職場応援団(厚生労働省)
令和6年12月10日開催「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」のアーカイブ動画を公開しました。(3/13)
今回のシンポジウムでは、企業のカスタマーハラスメント対策についての専門家による基調講演や、カスタマーハラスメント対策に取り組む企業の方から取組事例を紹介していただくパネルディスカッションなどを行いました。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium_2024
ITmedia ビジネスオンライン
初任給30万円時代、素直に喜べない「3つの落とし穴」とは(3/12)
初任給30万円時代の到来は、採用したい会社と好条件の内定を獲得したい学生の思惑が一致するだけに望ましく思われる。一方で、本当に手放しに喜べるものなのだろうか。
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2503/12/news070.html
「仕事を楽しめ!」が、部下をつぶしてしまうワケ(3/14)
「仕事を楽しめない」と感じている人や、部下育成で悩んでいるマネジャーは、ぜひ最後まで読んでもらいたい。
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2503/14/news095.html
愛知県
働く世代の健康づくり応援サイト(3/10)
事業所の健康管理ご担当者等向けに、この地域の健康に関する情報や従業員の健康づくりに役立つ情報をまとめました。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nishio-hc/chiikisyokuiki.html
経済産業省
中堅・中小成長投資補助金3次公募を開始しました。(3/10)
日本商工会議所
商工会議所ニュースかわら版No.145を発行(3/11)
- 東日本大震災からの「復興・創生」に関する要望 福島再生へ総力を
- 訪タイ・インドネシア経済ミッション ビジネス環境改善へ両国閣僚らと意見交換
- 日本YEG 第44回全国大会 ほとめき FUKUOKA くるめ大会 若きリーダー1万人が参加
https://www.jcci.or.jp/news/news/2025/0311163030.html
中小企業庁
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(3/11)
近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要です。
このため、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金の支払等の禁止、規制及び振興の対象となる取引への運送委託の追加等の措置を講ずるとともに、多段階の取引当事者が連携した取組等を支援し、価格転嫁・取引適正化を徹底していきます。
https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250311002/20250311002.html