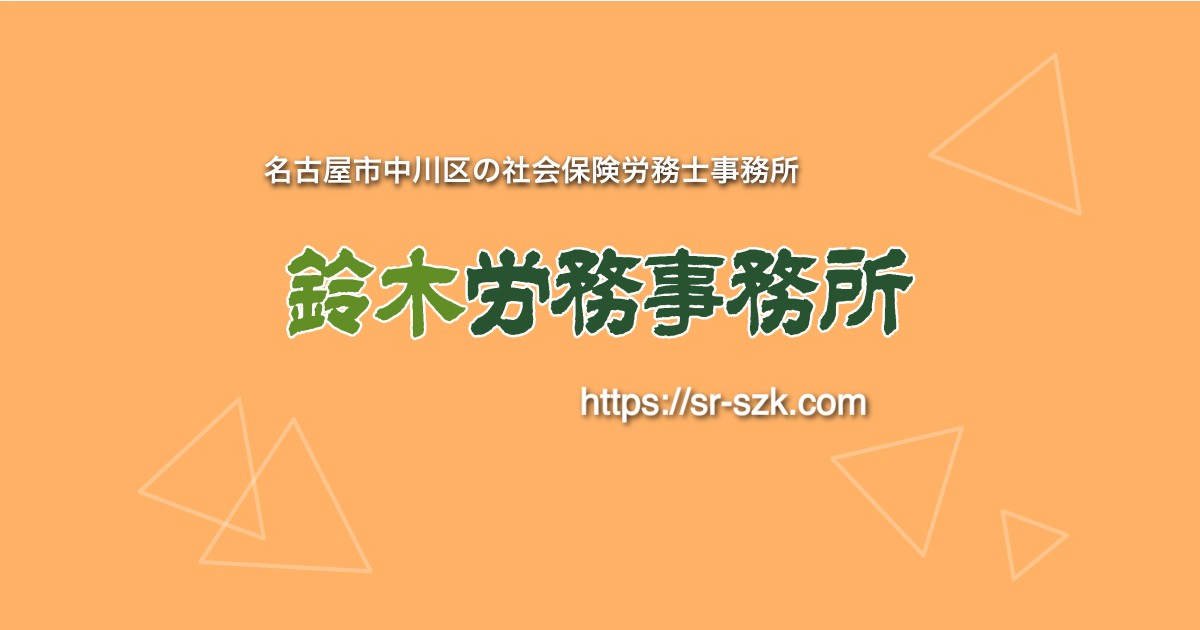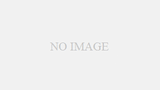退職金規程を作るときには、勤続年数の数え方を定めておくのが吉
「勤続年数0年と3か月」の社員を、あなたの会社では「0年」と数えますか? それとも「1年目」でしょうか?
たった数か月の違いと思われるかもしれませんが、退職金の計算においてこの“端数”の扱いは、実は制度全体の公平性や社員の納得感に影響を与える重要なポイントです。
退職金制度を導入・見直す際に、意外と見落とされがちなのが「勤続年数の数え方」です。「入社してから退職するまでの期間でしょ?」と考えがちですが、そのカウント方法に明確なルールを設けていないと、思わぬ誤解やトラブルにつながることがあります。
たとえば、入社から3か月経った社員の勤続年数を「0年」とするのか、「1年目」とみなして扱うのか――この考え方の違いによって、退職金の支給要件や金額に差が出る可能性があります。つまり、「満年数」で数えるのか、それとも「端数を切り上げて年目で数える」のか。どちらの方式を採用するかを事前に定めておく必要があるのです。
実際には、多くの企業が「満年数(端数切り捨て)」方式を採用しており、たとえば14年7か月働いた場合は「14年」として計算されるのが一般的です。
一方で、税務上の退職所得控除では「1年未満の端数は切り上げ」とされており、同じく14年7か月のケースでは「15年」として控除額が計算されます。
こうした会社の規定と税務上の扱いのズレは、社員からすると「なぜ税金では15年なのに、会社は14年しか認めないの?」と違和感につながりやすく、制度への不信や不満を招く可能性もあります。
企業としてはどちらを選ぶべきか?
どちらの方式を採用するかは、あくまで企業の判断に委ねられています。ただし、税務と同じ「切り上げ方式」に揃えることで、説明の手間が減り、社員にも納得されやすいというメリットがあります。
就業規則・退職金規程での明記例
第〇条(勤続年数の算定)
勤続年数は、入社日を起算日とし、退職日までの期間に基づき算定する。1年未満の端数がある場合は、これを1年に切り上げて算定するものとする。
このように明記しておくことで、いざ退職金を支給する際に「これは何年扱い?」という曖昧さを防ぐことができます。
退職金は社員の人生にとって大きな節目となるお金。だからこそ、その計算の根拠となる勤続年数の数え方についても、制度として丁寧に設計し、明文化しておくことが大切です。
小さな違いが、制度全体の信頼につながります。
【参考】(国税庁)退職手当等に対する源泉徴収:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
それでは今週のニュースPickupをどうぞ!!
厚生労働省
第3回 経済社会情勢の変化に対応したキャリアコンサルティングの実現に関する研究会資料(4/16)
- キャリアコンサルティングに必要な能力を得るための制度等について
- キャリアコンサルティングの活用活性化のための施策について
- 意見交換
- その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57109.html
人事労務マガジン特集第232号(4/16)
- 職場の雇用管理の改善(魅力ある職場づくり)に取り組む事業主の皆さまへ 人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)の受け付けを開始しました
- 2025年度「東京労働大学講座・総合講座」(5月開講/オンライン開催)受講者募集中
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56834.html
日本商工会議所
中小企業4団体連名による「最低賃金に関する要望」の公表について ~地方の中小企業・小規模事業者の経営実態を踏まえた政府方針検討・審議決定を~(4/17)
日本商工会議所・東京商工会議所(小林健会頭)、全国商工会連合会(森義久会長)、全国中小企業団体中央会(森洋会長)は連名で、標記要望を別添のとおり取りまとめましたので、お知らせいたします。
https://www.jcci.or.jp/news/recommendations/2025/0417170021.html
日本年金機構
【事業主の皆さまへ】令和7年度社会保険制度説明会の開催(4/15)
令和7年6月に「社会保険制度説明会」を開催します。本説明会では事業主、社会保険事務担当者の皆さまに向けた、さまざまなプログラムを用意していますのでぜひご参加ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/jimukoshukai.html
「日本年金機構からのお知らせ」令和7年4月号(4/18)
- 令和7年度社会保険制度説明会の開催
- 短時間労働者の適用拡大<被保険者資格取得届の届出漏れはありませんか>
- オンラインサービスを利用してみませんか? 他
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
e-Gov電子申請
健康保険証の新規発行終了に伴う申請・届出の新様式利用について(4/16)
日本年金機構から昨年12月に周知されている被保険者証廃止にともなう電子申請の様式変更について、旧様式による申請が令和7年2月28日をもって終了となりました。
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/2025-04-16t0952500900_1607.html
愛知県
起業家発掘・育成事業を実施します!~ACTIVATION Labが始動します!~(4/15)
STATION Aiメンバーの予備軍である起業に関心のある層を拡充し、エコシステムの発展を図るために、社会人を対象とした起業家発掘・育成事業「ACTIVATION Lab」を2023年度から実施しています。この事業では、社会人が起業に向けてステージに適したアクションができるように幅広い支援を提供しています。
https://www.pref.aichi.jp/press-release/startup-2025activatel1.html
ITmedia ビジネスオンライン
「転勤NG」は当然の権利? 拒否することの代償とは(4/14)
「転勤NG」の風潮が広まる中、転勤を拒むことのリスクについても冷静に考える必要がある。企業はなぜ、社員に転勤を命じるのか。社員にとって転勤は、どんな意味を持つのか。
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2504/14/news037.html
総務省
2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)3月分及び2024年度(令和6年度)平均(4/18)
- 総合指数は2020年を100として111.1
前年同月比は3.6%の上昇 - 生鮮食品を除く総合指数は110.2
前年同月比は3.2%の上昇 - 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は109.2
前年同月比は2.9%の上昇
!https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei08_01000309.html