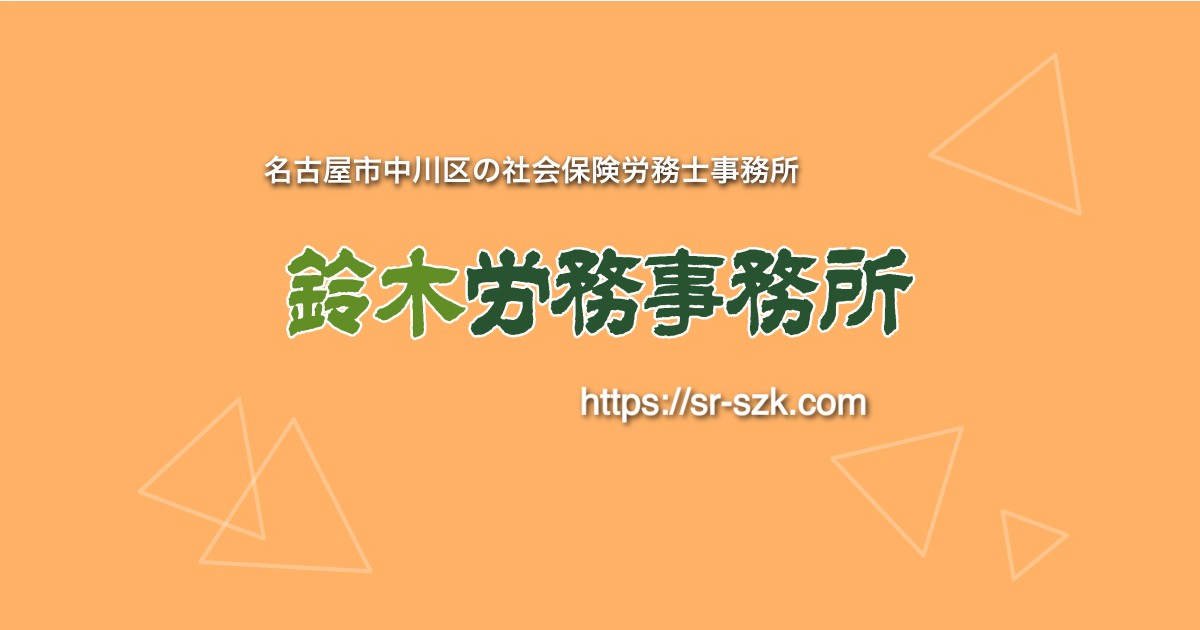賃上げ率、2年連続4%超え ── 中小にも広がる「賃上げの波」
厚生労働省が10月14日に公表した「令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、2025年中に賃金を「引き上げた・引き上げる」と回答した企業は全体の91.5%。前年(91.2%)をわずかに上回り、9割を超える企業で賃上げが実施されています。
今回から新たに「変わらなかった」という選択肢が設けられ、引き下げた企業1.1%・変わらなかった企業1.0%となりました。実質的な減額はごく一部で、いまや賃上げは例外ではなく日常になりつつあります。
■ 改定額・改定率ともに上昇傾向
- 平均引上げ額:13,601円(前年比+1,640円)
- 改定率:4.4%(同+0.3ポイント)
- 労働組合あり:4.8%(前年4.5%)
- 労働組合なし:4.0%(前年3.6%)
組合のない企業でも4%台に達しており、春闘の影響が中小企業にも広がっていることがうかがえます。また、2025年夏の賞与(平均1人当たり83万5,000円)も前年比約5%増となり、定期昇給とあわせて実質賃金を底上げする動きが見られました。
人手不足や物価高を背景に、「給与を上げないと人が来ない」「辞めてしまう」といった切実な現場の声が、結果として全体の賃金水準を押し上げている印象です。
■ 業種別では明暗も
- 製造業(5.2%)・建設業(5.9%)・電気ガス業(5.3%)は好調。
- 一方、宿泊・飲食(3.6%)・医療福祉(2.3%)・生活関連サービス(2.9%)は伸び悩み。
業種によっては、価格転嫁が難しい、採算が厳しいといった事情も見られます。
それでも、給与水準を少しでも上げようと工夫を重ねる現場の努力が感じられる結果といえるでしょう。
■ 定期昇給制度は8割超、評価反映型が主流に
定期昇給制度のある企業は81.2%。
内容をみると、
- 自動昇給:27.5%
- 業績・評価による昇給:72.4%
年功的な昇給から、成果や姿勢を評価する仕組みへと少しずつ変わってきています。業種別にみると特徴がはっきりしています。
- 製造業・電気ガス業では「自動昇給」比率が4割超と高く、技能継承や年次による熟練度を重視する傾向。
- 一方で、情報通信業・サービス業では「業績・評価昇給」が8割を超え、成果や行動評価を反映する動きが強まっています。
現場でも「昇給のルールを見直したい」という相談が増えており、単なる金額アップではなく、納得感のある賃上げを模索する流れが進んでいるようです。
■ これからの課題
平均4.4%という数字は心強いものの、「物価が上がる中で余裕はまだない」という声も多いのが現実です。
とはいえ、賞与の上積みや手当の工夫、評価ルールの明確化など、企業ごとにできる取り組みを続けることで、社員の意欲を支えられる余地は十分にあります。
賃上げの流れが一時的なブームに終わらず、職場の元気として根づいていくことを期待したいところです。
出典:厚生労働省|令和7(2025)年賃金引上げ等の実態に関する調査 結果の概要(10/14)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/25/index.html
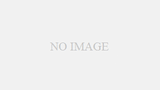
それでは今週のニュースPickupをどうぞ!!
国税庁|令和7年分 年調ソフト等の公開(10/16)
国税庁は、令和7年分の「年末調整ソフト」「年調クラウド」「API仕様書」などを公開しました。今年もe-Tax連携機能や控除額自動計算などの機能を備えており、従業員情報の入力負担を軽減できるよう設計されています。
🔎今週の視点
例年よりも早いタイミングでの公開となり、給与担当者にとっては年末調整準備のスタートが切りやすくなりました。システム対応を社内で分担して行う場合は、マイナポータル連携やXML形式の取込テストを早めに済ませておくと安心です。
出典:国税庁|令和7年分 年調ソフト等の公開(10/16)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
弁護士ドットコムニュース|「河合塾からクビを言い渡された」 50代で失業した講師が最高裁で「労働者性」を勝ち取るまでの12年(10/12)
大手予備校「河合塾」で働いていた50代男性講師が、雇い止めを不当として争った裁判で、最高裁は同社の上告を受理せず、講師の「労働者性」を認めた高裁判決が確定しました。裁判は12年に及び、講師の契約形態や勤務実態が詳細に審理されました。
🔎今週の視点
業務委託や請負といった「非雇用型」の契約が増える中で、実態として使用従属性がある場合には労働者性が認められる流れが強まっています。教育・研修・コンサル業などでも同様のケースはあり得るため、契約書だけでなく実際の働き方の管理が重要になりそうです。
出典:弁護士ドットコムニュース|「河合塾からクビを言い渡された」50代で失業した講師が最高裁で「労働者性」を勝ち取るまでの12年(10/12)
https://www.bengo4.com/c_18/n_19470/
ITmediaビジネスオンライン|20年以上の経験がある採用面接官が指摘「意味のない質問」とは?(10/15)
20年以上の経験を持つ採用担当者が、面接でよく見かける「意味のない質問」について指摘しています。「あなたの長所・短所は?」など、形式的な質問では本当の適性が見えにくく、むしろ面接官の側に準備不足があるといいます。
🔎今週の視点
中小企業では、面接官が面接慣れしていないことで、採用のミスマッチにつながる場合があります。形式よりも、「なぜこの仕事を選んだのか」「どんな時にやりがいを感じるか」といった会話を通じた理解を大切にしたいですね。
出典:ITmedia ビジネスオンライン|20年以上の経験がある採用面接官が指摘「意味のない質問」とは?(10/15)
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2510/15/news028.html