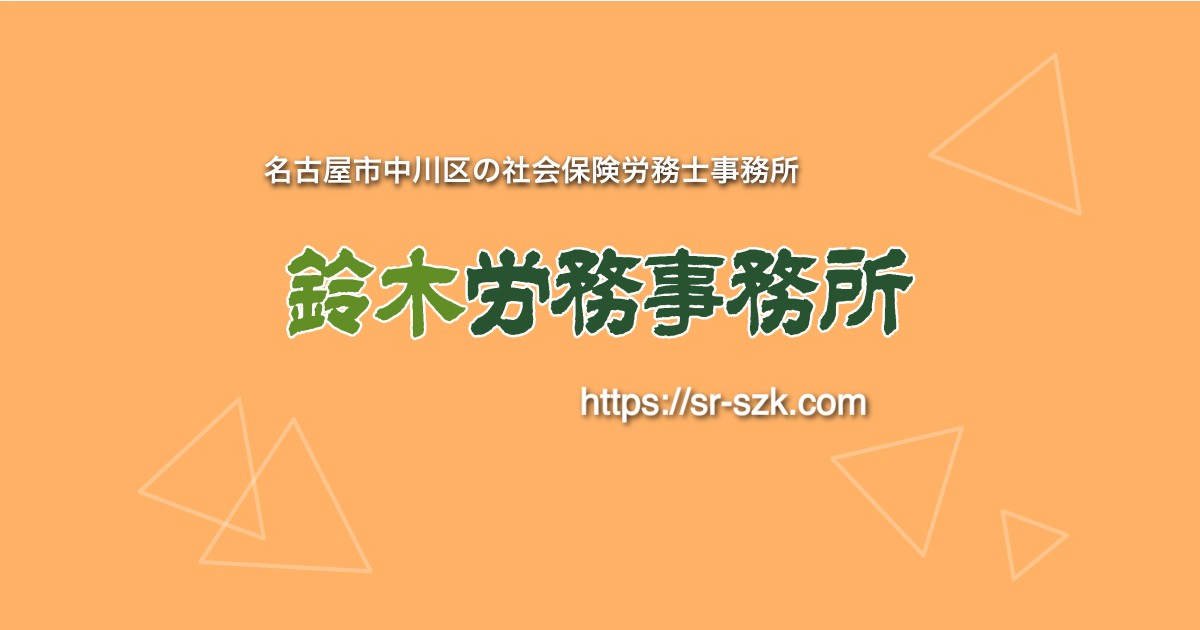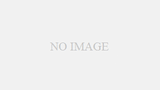小規模向け「ストレスチェック実施マニュアル案」が公表
11月10日、厚生労働省が「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」の資料を公表しました。その中に「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)」が含まれていました。今回、このマニュアル案を読み込んでみると、小規模事業場でも取り組みやすいよう、制度の基本的な流れから実務上の注意点までが整理されていることが分かります。まずはマニュアル案で示されているストレスチェックの全体像を簡単に確認しておきたいと思います。
ストレスチェック制度の全体的な流れ
1.実施体制の準備
担当者の決定や外部委託先の選定など、実施前に確認すべき事項がまとめられています。小規模事業場を前提に、必要最低限の準備項目が記載されています。
2.ストレスチェックの実施
厚労省の標準的な調査票の利用や、紙・オンラインいずれの方法にも触れられており、状況に応じて選択できるようになっています。
3.結果の通知
結果は本人に通知され、事業者が扱う場合は同意が必要となる点が示されています。通知の流れが分かりやすく整理されている印象です。
4.面接指導につなぐ流れ
高ストレス者の申し出に応じた面接指導の進め方が、産業医がいない場合も含めて説明されています。
5.職場環境の把握と改善
小規模事業場では集団分析が難しいことに配慮し、日頃の職場状況の把握を含めながら検討する方向性が示されています。
読み進めながら感じたのは、「できるだけ無理なく始められるように、必要な部分だけを丁寧に並べている」という姿勢でした。特に実施体制の部分は、外部委託の判断基準や委託先に確認しておくべき事項など、必要な項目が段階的に整理されていて、順に押さえていけば無理なく実施できそうだと感じました。
もうひとつ印象に残ったのが、「結果をどう活かすか」の部分です。ストレスチェックというと実施することに意識が向きがちですが、マニュアル案ではその後の対応が手順として分かりやすく示されています。高ストレス者への対応の流れや、面接指導のつなぎ方、個人情報を守りつつ必要なコミュニケーションを確保する方法など、リアルな場面をイメージできる内容です。
また、小規模事業場での職場環境の改善について、数字に表れない変化を観察する姿勢が重要だとされている点も特徴的でした。ストレスチェックの結果を、日々の働き方やコミュニケーションの見直しにさりげなく役立てていける内容だと思いました。
今回公表されたものはまだ「案」の段階であり、正式版が公表される時には内容が変更される可能性がある点に注意が必要ですね。
出典:厚生労働省|ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第4回資料(11/10)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65743.html
それでは今週のニュースPickupをどうぞ!!
明るい職場応援団サイト(厚生労働省)|令和7年12月10日に「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。参加申込み受付を開始しました。(12/10)
職場でのハラスメント対策をテーマとしたオンラインシンポジウムが、12月10日に開催されます。今回はカスタマーハラスメントへの取組に焦点を当て、業界団体による事例紹介やパネルディスカッションが予定されています。実務担当者が最新の動向や他社の取組を知る機会として活用できそうです。
🔎 今週の視点
カスタマーハラスメントは業種を問わず相談が増えているテーマで、特に接客業や公共サービスでは対応が難しい場面も多いようです。シンポジウムで他社の事例に触れることで「どこまで対応すべきか」「組織として何を決めておくべきか」が見えやすくなるのではないでしょうか。オンラインでの開催ですので、情報収集の機会として参加してみる価値はありそうですね。
出典:明るい職場応援団サイト(厚生労働省)|令和7年12月10日に「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。参加申込み受付を開始しました。(12/10)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium
経済産業省|「中小企業向け 仕事と介護の両立支援セミナー」を配信します(11/11)
育児・介護休業法の改正内容や、人的資本経営との関係性、企業が押さえておきたいガイドラインについて解説するセミナーが配信されました。介護との両立支援は中小企業で特にニーズが高く、経営側の理解を深める内容となっています。
🔎 今週の視点
介護は突然始まることが多いため、その時になって慌てなくてもいい様に普段から意識しておくことが重要です。制度の知識を持っておくことで、急な相談にも落ち着いて対応できるようになります。
動画で学べるので少し時間が空いた時に見るのも効果的ですね。担当者だけでなく、社内研修の素材として活用するのも一つの方法ではないでしょうか。
出典:経済産業省|「中小企業向け 仕事と介護の両立支援セミナー」を配信します(11/11)https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251111004/20251111004.html
全国健康保険協会|事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(11/14)
協会けんぽでは、令和7年度の被扶養者資格再確認を実施します。事業主には「被扶養者状況リスト」が送付され、記載内容を確認のうえ返送する必要があります。被扶養者が要件を満たしているかどうか、年1回の確認が求められます。
🔎 今週の視点
そろそろ各会社に書類が届いている頃です。提出期限まで余裕を持ったスケジュールを組んだり、従業員への事前周知を行っておくことで、確認漏れや差し戻しを減らすことができるでしょう。年末調整と重なる時期でもあるため、計画的に進めたいところです。
出典:全国健康保険協会|事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(11/14)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info251017/
愛知労働局|愛知県の特定最低賃金(2業種)を引上げます(11/14)
製鉄業・鋼材製造業は1,175円、輸送用機械器具製造業は1,146円へと、それぞれ令和7年12月16日から改定されます。
🔎 今週の視点
最低賃金の改定は既に全国で実施済みですが、業種別の特定最低賃金も忘れず確認し、必要に応じて賃金改定などの対応が必要ですね。
出典:愛知労働局|愛知県の特定最低賃金(2業種)を引上げます(11/14)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/oshirase.html
経団連|労働時間規制に関する経団連の主張(11/10)
経団連は、労働時間規制について従来からの主張が変わっていないことを改めて公表しました。働き方改革法制が続く中、企業側団体として一貫した立場を維持していることを示す内容となっています。
🔎 今週の視点
新しい政府になり、長時間労働についての話題がニュースを賑わせています。
経済界の主張を押さえておくことで、今後の政策議論の方向性を読みやすくなるかもしれません。企業としても、長時間労働の是正や生産性向上への取り組みを継続していく必要がありそうですね。
出典:経団連|労働時間規制に関する経団連の主張(11/10)
https://www.keidanren.or.jp/policy/2025/078.html